kangaeru hana
















































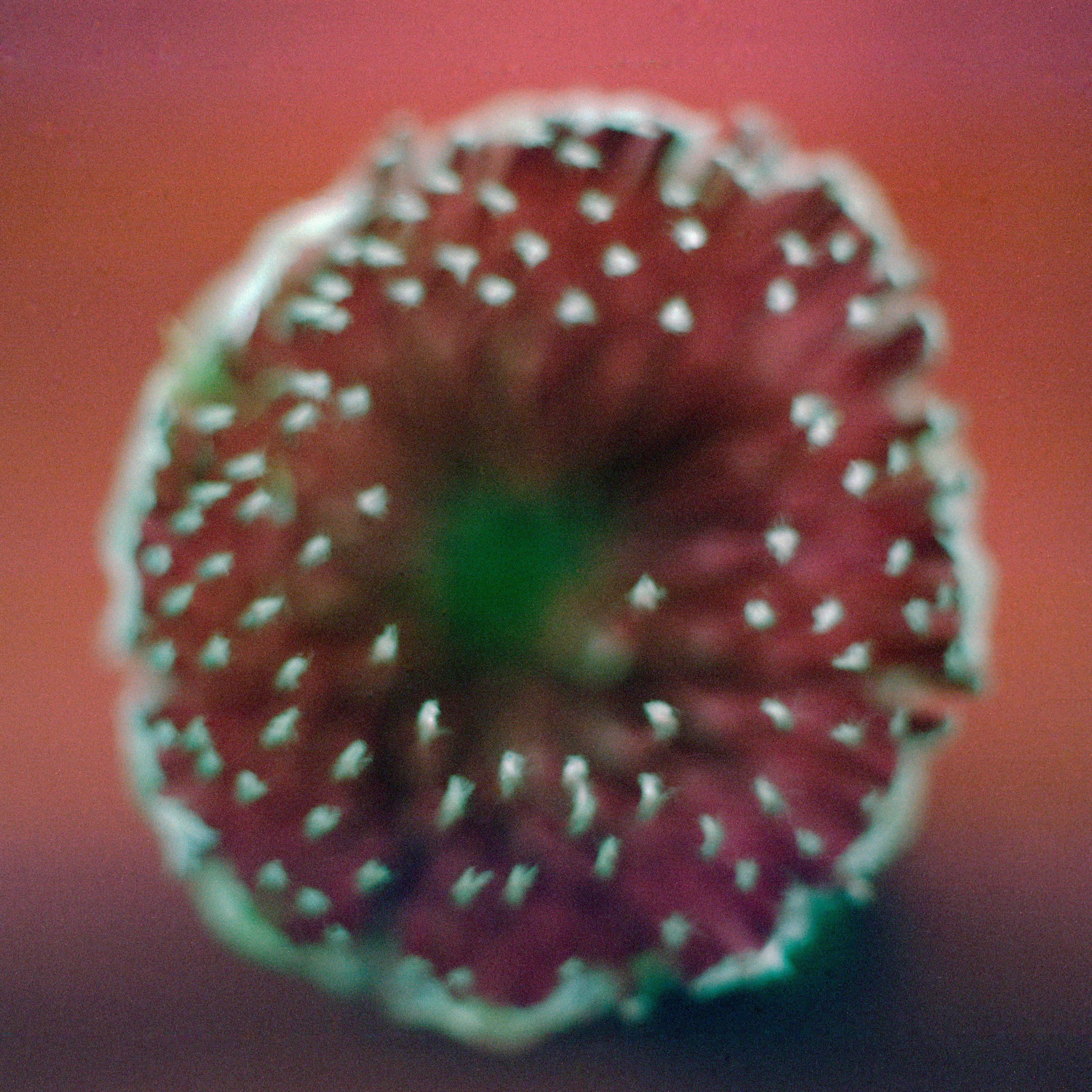





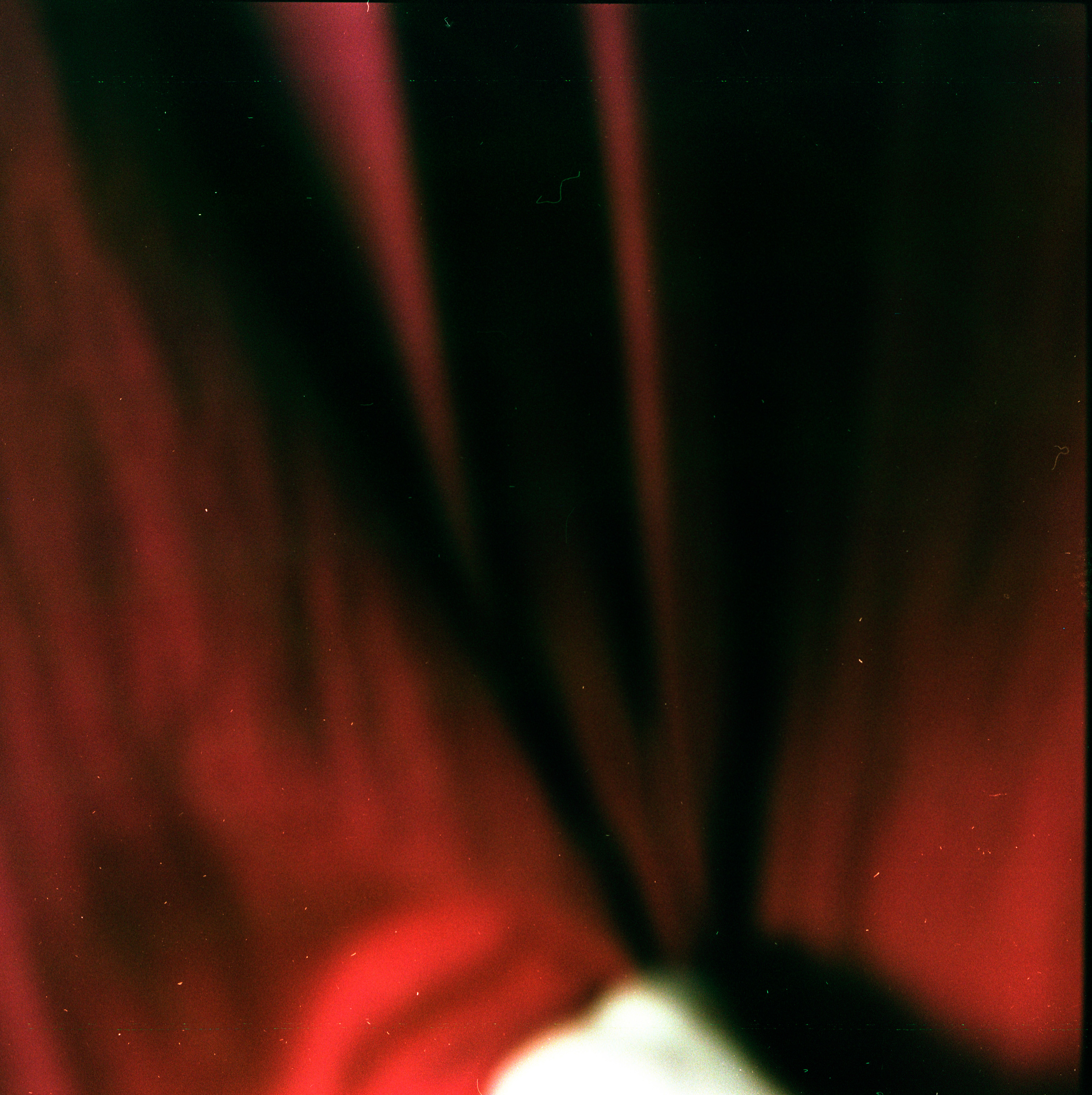











kangaeru hana
写真はいつ生まれるのか。
僕は一つの考えを持っている。
『次のようなものは存在しない。
a.他の諸概念に対して、あらかじめ出来上がっていて、全く別物であるような観念。
b.このような観念に対応する記号(シーニュ)。
そうではなくて、言語記号が登場する以前の思考には、何一つとして明瞭に識別
されるものではない。これが重要な点である。』
これは近代言語学者フェルディナン・ド・ソシュールの『一般言語学講座』からの抜粋だ。言語はアプリオリな純粋概念に被覆しているようなものではないと述べている。彼が考える言語記号とは次のようなものだ。例えば『雨上がりの空に浮かぶカラフルな弓状のもの』を日本では虹と言う。この場合『雨上がりの空に浮かぶカラフルな弓状のもの』という実態が記号内容、『虹、にじ』という文字や音が記号表現。私たちは(にじ)という音を聞いたり(虹、にじ)という文字を見ると『雨上がりの空に浮かぶカラフルな弓状のもの』をイメージする。このように内容と表現が対になったものが言語記号だ、とソシュールは言う。
さて写真はどうだろう。右を写真に当てはめると『像』が記号内容、見た人の『解釈』が記号表現にあたる。ここで大切なことは、その『像』自体に内包されているのはあくまで(記号内容)のみであるということだ。『解釈』(記号表現)は誰かが像を見た後に生まれるのだ。『像』自体は様々な可能性は持っているが、その表現を決定していない。先も述べたように言語記号は、(記号内容)と(記号表現)が対になって初めて言語記号になる。それを写真に置き換えて考えれば、何者かが『像』を見て何らかの『解釈』をした段階、つまり(記号内容)と(記号表現)が対になったときに、『像』は初めて写真となるのだ。
ここではじめの問いに戻る。
写真はいつ生まれるのか。
シャッターを切る時、フィルムに露光する時、印刷する時、それとも想像した時だろうか。
いや、写真は『誰かがその像を見た時』に生まれるのだ。
「考える花」は、もし花が思考しているのならば、その思考はどこにあり、何によってなされているのだろうかという問いだ。その文章記号と可視化の試みが今回の個展の一連の像である。これらの像は一見矛盾していたり、不安定であったり、近すぎたり遠すぎたりと、「不条理」がまとわりつく。
仮に一つの像を一億人が見たとき、一億個の解釈が生まれたとする。つまり一つの像から一億の写真が生まれたと言うことだ。この場合、その像が保有する記号内容は、極限まで曖昧模糊としていると言えるだろう。しかし、一つの像を見て一つの解釈しか生まない像もある。広告写真はその最たるものである。とにかく「考える花」では、わかりやすい記号を使用しないことにしている。そうやってつくられた一連の像は不条理を備えている。なぜ僕は(そんな)像を撮るのか。
想像して欲しい。(そんな)像を見た者は戸惑い考えてしまう。朦朧とした記号を前に、彼、彼女は無意識に撮影者の意図を探り始めるのだ。しかし他人の意図を推し量る時、その人は自らの内側にある情報を手掛かりに考察する他に方法がない。(そんな)像を見た者は撮影者の思考を覗き見ているつもりのようで、実は自らの脳を掻き分け見つめているにすぎないのだ。
人は不可解なものを前にしたときに、自分の中の静寂を聞くことになるのだ、とマグリットは言った。これに同意すれば、僕はつまるところ静寂を撮っていると言うことになる。カメラ機械をつかい、この世に存在しているものを切り取ったはずなのに、写し出された像はこの世のものではない一つの静寂めいた無形だ。この理不尽で不可解な現象を、なんとも面白いと思うのは僕だけなのだろうか。
僕は一つの考えを持っている。
『次のようなものは存在しない。
a.他の諸概念に対して、あらかじめ出来上がっていて、全く別物であるような観念。
b.このような観念に対応する記号(シーニュ)。
そうではなくて、言語記号が登場する以前の思考には、何一つとして明瞭に識別
されるものではない。これが重要な点である。』
これは近代言語学者フェルディナン・ド・ソシュールの『一般言語学講座』からの抜粋だ。言語はアプリオリな純粋概念に被覆しているようなものではないと述べている。彼が考える言語記号とは次のようなものだ。例えば『雨上がりの空に浮かぶカラフルな弓状のもの』を日本では虹と言う。この場合『雨上がりの空に浮かぶカラフルな弓状のもの』という実態が記号内容、『虹、にじ』という文字や音が記号表現。私たちは(にじ)という音を聞いたり(虹、にじ)という文字を見ると『雨上がりの空に浮かぶカラフルな弓状のもの』をイメージする。このように内容と表現が対になったものが言語記号だ、とソシュールは言う。
さて写真はどうだろう。右を写真に当てはめると『像』が記号内容、見た人の『解釈』が記号表現にあたる。ここで大切なことは、その『像』自体に内包されているのはあくまで(記号内容)のみであるということだ。『解釈』(記号表現)は誰かが像を見た後に生まれるのだ。『像』自体は様々な可能性は持っているが、その表現を決定していない。先も述べたように言語記号は、(記号内容)と(記号表現)が対になって初めて言語記号になる。それを写真に置き換えて考えれば、何者かが『像』を見て何らかの『解釈』をした段階、つまり(記号内容)と(記号表現)が対になったときに、『像』は初めて写真となるのだ。
ここではじめの問いに戻る。
写真はいつ生まれるのか。
シャッターを切る時、フィルムに露光する時、印刷する時、それとも想像した時だろうか。
いや、写真は『誰かがその像を見た時』に生まれるのだ。
「考える花」は、もし花が思考しているのならば、その思考はどこにあり、何によってなされているのだろうかという問いだ。その文章記号と可視化の試みが今回の個展の一連の像である。これらの像は一見矛盾していたり、不安定であったり、近すぎたり遠すぎたりと、「不条理」がまとわりつく。
仮に一つの像を一億人が見たとき、一億個の解釈が生まれたとする。つまり一つの像から一億の写真が生まれたと言うことだ。この場合、その像が保有する記号内容は、極限まで曖昧模糊としていると言えるだろう。しかし、一つの像を見て一つの解釈しか生まない像もある。広告写真はその最たるものである。とにかく「考える花」では、わかりやすい記号を使用しないことにしている。そうやってつくられた一連の像は不条理を備えている。なぜ僕は(そんな)像を撮るのか。
想像して欲しい。(そんな)像を見た者は戸惑い考えてしまう。朦朧とした記号を前に、彼、彼女は無意識に撮影者の意図を探り始めるのだ。しかし他人の意図を推し量る時、その人は自らの内側にある情報を手掛かりに考察する他に方法がない。(そんな)像を見た者は撮影者の思考を覗き見ているつもりのようで、実は自らの脳を掻き分け見つめているにすぎないのだ。
人は不可解なものを前にしたときに、自分の中の静寂を聞くことになるのだ、とマグリットは言った。これに同意すれば、僕はつまるところ静寂を撮っていると言うことになる。カメラ機械をつかい、この世に存在しているものを切り取ったはずなのに、写し出された像はこの世のものではない一つの静寂めいた無形だ。この理不尽で不可解な現象を、なんとも面白いと思うのは僕だけなのだろうか。